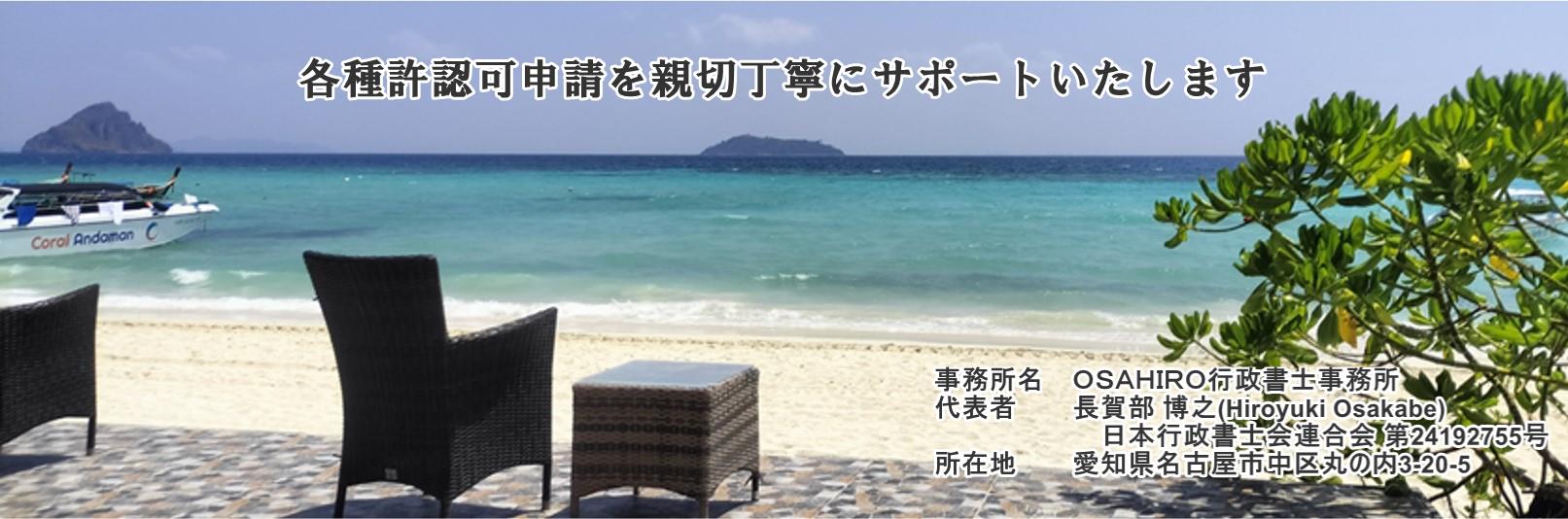
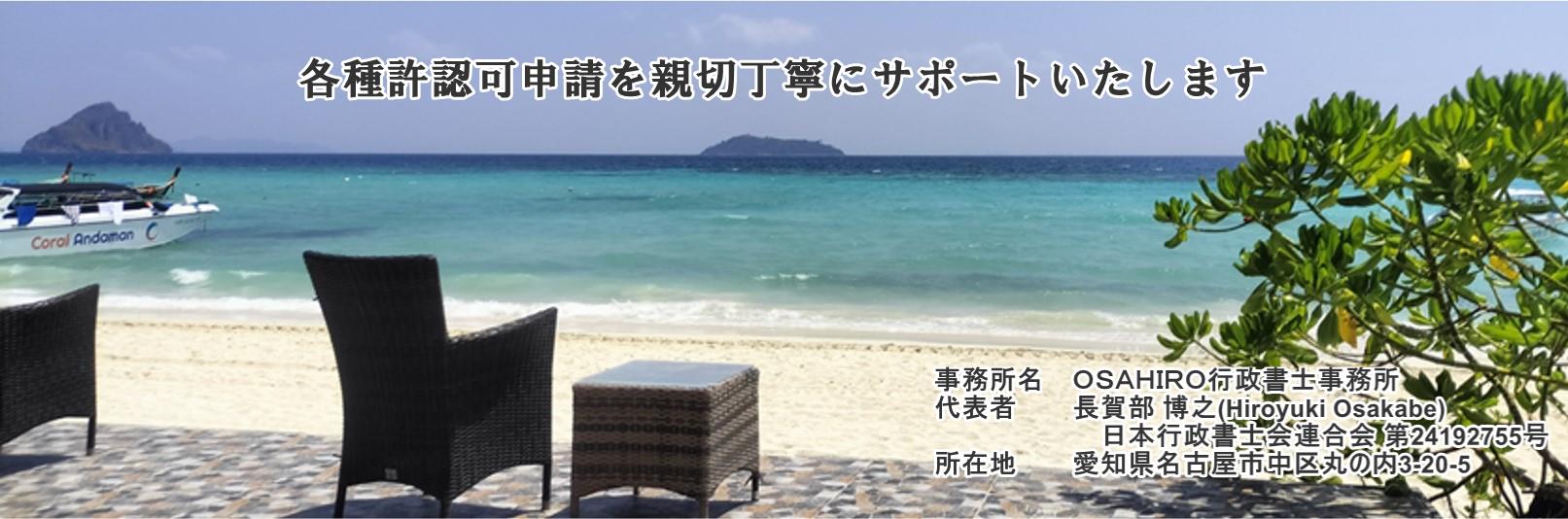
放課後等デイサービス|名古屋市

放課後等デイサービス事業を開始するには、事業所が所在する都道府県知事(指定都市においては当該市長)の指定を受ける必要があります。多くの書類を収集したり作成したりして申請することになります。名古屋の「OSAHIRO行政書士事務所」では、放課後等デイサービス事業の指定申請をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。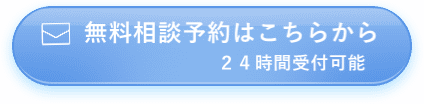
指定を受けるための要件
放課後等デイサービスの指定申請は、人員、設備、運営の各基準を満たし、所定の手続きを経て行われます。特に運営基準においては、個別支援計画や支援プログラムの質、身体拘束等の廃止、BCP策定、関係機関との連携などが重要視されています。適切な申請準備と基準の遵守は、事業の開始だけでなく、質の高い支援を提供し継続していくために不可欠です。
人員基準
| 人数 | 概要 | |
| 管理者 | 常勤1名 | 事業所の管理業務を行う責任者。他の職務との兼務が可能です。 |
| 児童発達支援管理責任者(児発管) | 常勤1名 | 障害児支援利用計画に基づき、個別支援計画の作成等を行う専門職。知識や経験などの資格要件があります。 |
| 児童指導員・保育士 | 2名以上(利用者10名以下の場合) | 直接支援を行う職員。利用者数が5名増えるごとに1名追加が必要です。1名以上は常勤である必要があります。 |
| 機能訓練担当職員 | 必要な機能訓練を行う場合に配置 | 専門的な機能訓練を提供する職員。児童指導員・保育士の人員配置人数に含めることができる場合があります。 |
※ 常勤:原則として事業所の就業規則等に定められた常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を基本とするが、週30時間以上で認める場合あり)。育児・介護短時間勤務制度や治療と仕事の両立ガイドラインに沿った短時間勤務制度を利用する場合も、週30時間以上の勤務で常勤として扱われることがあります。
※ 人員基準を満たさない場合、報酬が減算されることがあります。
設備基準
| 設備の種類 | 概要 |
|---|---|
| 指導訓練室 | 支援プログラムに基づいた活動を行うためのスペースです。 |
| その他必要な設備 |
相談室、事務室、便所など。事業の種類によって必要な設備は異なります。 |
運営基準
◇ 個別支援計画の作成・見直し
・利用者一人ひとりのニーズに基づき、児童発達支援管理責任者(児発管)が作成します。
・計画作成にあたっては、こどもの最善の利益が優先的に考慮され、その意思が尊重されるよう配慮が必要です。
・インクルージョン(障害の有無にかかわらず全ての児童が共に成長できる地域社会への参加・包摂)の推進に努め、計画にその観点や具体的な取組(保育所等への移行支援や地域交流等)を明記することが求められます。
・支援内容は、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にして記載する必要があります。
・「本人支援」「家族支援」「移行支援」は必ず記載し、「地域支援・地域連携」は必要に応じて記載しますが、関係者が連携して支援する観点から積極的に取り組むことが望ましいとされています。
・計画は6ヶ月に1回以上の見直しが必要です。
◇ 支援プログラムの作成・公表
・事業所全体の支援内容を示すプログラムを作成し、公表が義務付けられます。未実施の場合は報酬が減算されます。
・プログラムには、事業所名、理念、支援方針、営業時間、送迎の有無、本人支援(5領域との関連性)、家族支援、移行支援、地域支援・地域連携、職員の質向上に関する取組などが含まれます。
◇ 身体拘束等の廃止・適正化
・緊急やむを得ない場合を除き身体拘束は禁止されています。
・適切な記録、検討委員会の定期的開催(年1回以上)、指針整備、研修の定期的実施(年1回以上)が必要です。
・適切な取組が行われていない場合、報酬が減算されます。
◇ 業務継続計画(BCP)の策定
・感染症や非常災害発生時でもサービスを継続提供できるよう、BCPの策定が義務化されます。未策定の場合、報酬が減算されます。
◇ 関係機関等との連携
・市町村、相談支援事業所、学校、保育所、医療機関など、様々な関係機関との連携が重要です。複数の事業所を利用する子どもについては、事業所間の連携が特に重要です。
◇ 虐待防止
・職員は虐待の早期発見に努め、虐待が疑われる場合は速やかに市町村や児童相談所等へ通報・通告する義務があります。
◇ その他
・こどもの心身の状況や置かれている環境、意向を踏まえ、多様な事業者からのサービス利用を含めて支援計画に位置付けるよう努めることが求められます。
・常勤要件等について、育児・介護等短時間勤務制度や治療と仕事の両立のための短時間勤務制度を利用する場合、一定の条件を満たせば常勤として扱うことが可能です。
・管理業務以外の職種・業務について、個人情報管理や処遇に支障がないことを前提にテレワークの活用が可能です。
指定申請の流れ
新規指定申請の一般的な流れは以下の通りです。自治体によって詳細は異なる場合があります。
1.事前協議
原則として、新規指定申請前には事前協議が必要です。事業計画や人員・設備の基準適合状況について、事前に確認・相談を行います。居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援は事前協議が不要です。
2.申請書類提出
事前協議が整った後、指定申請書類を提出します。愛知県の場合、原則として申請月の月末が締切です。
3.審査・実地確認
提出された書類に基づき、基準を満たしているか審査が行われます。必要に応じて、事業所の設備などが基準を満たしているか実地確認が行われることがあります。
4.補正対応
審査の過程で書類や内容に不備があった場合、指摘事項に対して補正(修正や追加提出)を行います。
5.指定
基準を満たしていることが確認されると、指定が行われます。指定は原則毎月1日です。愛知県の場合、申請月の翌々月1日に指定となります。
申請にあたっての主な注意点
基準適合
人員、設備、運営の各基準を満たしていることが必須です。基準を満たさない場合、指定が先送りになったり、指定後も減算の対象となる場合があります。
計画・プログラム
個別支援計画や支援プログラムの作成・公表は運営基準で求められています。これらの計画やプログラムに基づいた適切な支援が重要視されています。
安全対策・衛生管理
送迎時の子どもの所在確認や安全装置の装備、駐車場の確保、食事提供を行う場合の保健所への手続き、医療的ケア児への適切なケア提供体制 など、安全・衛生管理は重要です。
各種加算・減算
医療的ケア児、重症心身障害児、強度行動障害、要保護・要支援児童など、特定のニーズを持つ子どもへの支援に対する加算 や、適切な運営を行わない場合の減算 が複数規定されています。これらの内容を理解し、適切に対応することが経営上も重要です。
連携の促進
セルフプランで複数事業所を利用する子どもに関する事業所間連携加算 や、各種関係機関との連携を評価する加算 など、関係機関との連携が多方面で評価されています。








